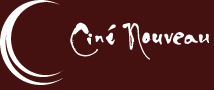|
若尾文子が大映に入社したとき、社長の永田雅一から、『映画スターは“高嶺の花”と言われているが、お前はヒク嶺の花だ。だれにでも手の届きそうなところが身上だ』と言われたという。いかにも永田ラッパらしい、身も蓋もない言い草だが、「ヒク嶺の花」に続くセリフは、案外、若尾文子の行く末を言い当てていたかもしれない。そう、彼女は、だれにでも手が届きそうな女優として歩みはじめ、さまざまな作品に出て、経験を重ねるうちに、高嶺の花のままでは辿りつけない「女」、男の理解や思い込みを遙かに超えた、他者なるものとしての「女」を体現するに到ったのではないか。
シネ・ヌーヴォの特集では、早い時期の作品も並んでいるが、わたしが憶えているのは、溝口健二監督の『祇園囃子』(53年)ぐらいだ。舞妓志願の彼女が、木暮實千代のもとを訪ねた最初の登場場面、その初々しい姿は鮮やかに記憶に残っている。その頃には、彼女はブロマイドの売れ行き1番の人気になっていたというが、アメリカのギャング映画を追いかけていた当方には、関わりはござんせん。彼女に注目するようになったのは、やはり、60年代になってからだ。それも、若尾文子という女優の内に眠っていた可能性を最大限に引き出した増村保造監督とのコンビにおいて。
決定的なのは、『妻は告白する』(61年)だが、その前の『偽大学生』(60年)での女子大生役も印象深い。ジェリー藤尾の偽大学生を吊し上げる学生集団の中で、何をするというのではないが、得も言われぬ疲労感を漂わせた表情が素晴らしい。それは、中国戦線での看護婦を演じた『赤い天使』(66年)にも通じる。『妻は告白する』での、男をたじろがせる情念のうねりとともに、そんな自身の身体を持て余しているかのような疲労感。それは、少しも邪気を感じさせない笑顔によぎる影のように、男を惹きよせ、惑わせる。ここに、他者としての「女」、若尾文子がいる! |
|