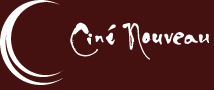|
1960年代はやくざ映画が、1970年代は,ロマンポルノが日本映画のベースだった。むろん、それ以外にも,いろいろな映画があったのだが、娯楽映画の基調を決めていたのは、それらの映画だ。
では、1980年代は何かといえば、これがはっきりしないのだ。角川映画やテレビ局主導の大作映画があるかと思えば、大森一樹や森田芳光のような、自主映画出身の監督たちによる小規模の映画もありと、雑多で、とても一つの傾向や色合いで括ることが出来ないのだ。そうなった背景には、それまで日本の映画産業を中心的に担ってきた映画会社の衰退があった。
映画の製作から,配給、興業まで一手に握ってきた映画会社の衰退と機を一にして現れたのが、独立プロデューサーという存在である。今回の特集の元になった伊藤彰彦さんの本の主人公というべき岡田裕氏しかり。彼の元に集まったプロデューサーたちしかり。いずれも、日活の経営が傾いたのを機に、独立して映画の製作に当たるようになったのだ。彼らより一足早く独立した黒沢満氏や、伊地知啓氏もいる。さらに出版界から映画製作に乗り出した角川書店の角川春樹氏もいる。また、鈴木清順を復活させた荒戸源次郎もいた。80年代は、そのような独立プロデューサーの時代だったのだ。
独立プロデューサーは、それまで、映画会社が得意としてきたジャンルや方向性にとらわれることなく、各自が、むろん、製作に伴うリスクや興業展開を勘案しつつも、独自の好みや志向によって題材を選び、それに相応しいと思われる監督や出演者を決めていったのだ。その結果が、80年代の、一見、雑多でもあれば、自由で多様な映画を産み出していったのである。今回、シネ・ヌーヴォで上映される13本は、外国と連携することの難しさを背負った大作『復活の日』をはじめ、いずれも岡田裕氏が陰に陽に関わった作品だが、それぞれの映画が発する色合いや匂いは、実に多種多様である。 |
|